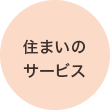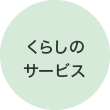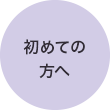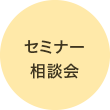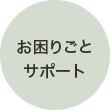耳より情報
2025年04月30日 [耳より情報]
土地を相続したけど手放したい!「相続土地国庫帰属制度」とは?

オーケストライフでは、皆さまのお役に立てるくらしや住まいの耳より情報を定期的に発信していきます。今回は、地域の頼れる不動産アドバイザー トラストバンク株式会社の齋藤 健児が「土地を相続したけど手放したい!『相続土地国庫帰属制度』とは?<前編>」と題して、お話しします。
先日、以前よりお付き合いのあるお客さま(Aさん)から、「ちょっと、齋藤さんにご相談したいことが……」と連絡がありました。話を聞いてみたところ、『田舎に住む両親が相次いで亡くなり、土地を相続した。土地といっても両親もずっと使用していなかった農地で、今後ほかの誰かが利用するとも思えない。どうすれば良いか?』という内容でした。
さっそく、Aさんと私、トラストバンク齋藤の会話をもとに、今回ご紹介する制度について紹介していきます。
Aさん:
齋藤:
Aさん:
齋藤:
【相続土地国庫帰属制度】とは?
相続によって土地(山林や農地なども含む)の所有権を相続した人が、ある一定の要件を満たした場合、土地を手放し国に引き渡す(国庫に帰属させる)制度のこと
【制度を利用できる土地の要件】とは?
国庫への帰属が認められる土地は、法令で定める却下事由(申請の段階で却下)と不承認事由(申請しても承認されない)のいずれにも当てはまらないものに限られます。どんな土地でも国庫帰属として認められるわけではないのです。では、国庫帰属が認められない土地(制度を利用できない)とは、どのようなものなのでしょうか?
<申請の段階で却下される土地>
●建物のある土地
●担保件などが設定されている土地
●汚染されている土地
●通路などが含まれる土地
●境界が明らかでない土地など、所有権について争いがある土地
<申請しても不承認となる土地>
●有体物が地下にある土地
●管理が大変な崖がある土地
●管理や処分を阻止する有体物がある土地
●管理や処分をするのに過分の労力や費用が必要な土地
●ほかの土地への通行が妨げられている土地
●所有権に基づいた使用、収益が妨害されている土地
【申請できる人】は?
相続や遺贈で土地を取得した相続人
※兄弟で相続するなど共有となっている土地についても申請は可能。その場合には、共有者全員で申請する必要がある。
※施行前に相続した土地でも申請可能
【申請手続きの流れ】は?
① 法務局に相談
→土地の所在地を管轄する法務局、もしくは地方法務局に相談へ
② 申請書類の作成、提出
→必要となる書類を作成の上、提出。ここで審査の際に必要な手数料を納めた上、承認申請を行う
(審査手数料/土地1筆当たり1万4000円)
③ 審査(実地調査)
→申請書類を審査し、必要に応じて土地の実地調査が行われる
④ 承認結果の確認
→承認結果を受け、承認された際は負担する金額が伝えられる
⑤ 負担金の納付
→負担金額の通知があってから30日以内に納付する
▶ 法務省のホームページもあわせてご確認ください。
▶ 法務省の資料PDFはこちら
以上、大まかな【相続土地国庫帰属制度】の概要をお届けしました。不要な土地を管理するには大きな負担がかかります。かといって引き渡し先を探し続けたとしても、大きな時間やコストがかかってきます。こういった面からも【相続土地国庫帰属制度】を利用することで、それらが軽減されるでしょう。
ただし制度を利用する場合でも、もちろん費用は必要です。そこで続く後編では、気になる「相続土地国庫帰属制度」の費用面について深掘りしてゆきます。どうぞお楽しみに!
「利用しない土地を相続して悩んでいる」(Aさんのケース)
さっそく、Aさんと私、トラストバンク齋藤の会話をもとに、今回ご紹介する制度について紹介していきます。
Aさん:
実はこの土地、最近までは近隣に住む親戚が管理してくれていたのですが、「そろそろ、どうするか考えてほしい」と言われたんです。私もつい、甘えてここまできてしまい……。
齋藤:
なるほど~。それは悩ましいですね。現地の様子を見ていないので断定できませんが、土地の価値が低く需要が少ないと、やはり買い手はつかないのが現状です。結果的に「売却が難しい土地」と判断せざるを得ないかもしれません。
Aさん:
固定資産税や管理に関する費用などの支払いも発生する……。使用しない土地は、「負(ふ)動産」なんて言い方も耳にしますが、まさに今、それを実感しています。「それなら、相続放棄すべきだったのか?」とも思いましたが、そうなると土地以外の財産も手放す必要があるんですよね?(特定の財産だけを手放すことはできない)
齋藤:
おっしゃるとおりです。相続放棄すれば、土地だけでなく預貯金や株式などすべての相続権も失うことになりますからね。令和5年4月27日より制度が開始となった【相続土地国庫帰属制度】をご存知ですか? 実際にAさんの土地が条件に当てはまるかは分かりませんが、相続した土地を国へ引き渡すことができるこちらの制度をご紹介します。
「相続土地国庫帰属制度」について解説
相続によって土地(山林や農地なども含む)の所有権を相続した人が、ある一定の要件を満たした場合、土地を手放し国に引き渡す(国庫に帰属させる)制度のこと
【制度を利用できる土地の要件】とは?
国庫への帰属が認められる土地は、法令で定める却下事由(申請の段階で却下)と不承認事由(申請しても承認されない)のいずれにも当てはまらないものに限られます。どんな土地でも国庫帰属として認められるわけではないのです。では、国庫帰属が認められない土地(制度を利用できない)とは、どのようなものなのでしょうか?
<申請の段階で却下される土地>
●建物のある土地
●担保件などが設定されている土地
●汚染されている土地
●通路などが含まれる土地
●境界が明らかでない土地など、所有権について争いがある土地
<申請しても不承認となる土地>
●有体物が地下にある土地
●管理が大変な崖がある土地
●管理や処分を阻止する有体物がある土地
●管理や処分をするのに過分の労力や費用が必要な土地
●ほかの土地への通行が妨げられている土地
●所有権に基づいた使用、収益が妨害されている土地
【申請できる人】は?
相続や遺贈で土地を取得した相続人
※兄弟で相続するなど共有となっている土地についても申請は可能。その場合には、共有者全員で申請する必要がある。
※施行前に相続した土地でも申請可能
【申請手続きの流れ】は?
① 法務局に相談
→土地の所在地を管轄する法務局、もしくは地方法務局に相談へ
② 申請書類の作成、提出
→必要となる書類を作成の上、提出。ここで審査の際に必要な手数料を納めた上、承認申請を行う
(審査手数料/土地1筆当たり1万4000円)
③ 審査(実地調査)
→申請書類を審査し、必要に応じて土地の実地調査が行われる
④ 承認結果の確認
→承認結果を受け、承認された際は負担する金額が伝えられる
⑤ 負担金の納付
→負担金額の通知があってから30日以内に納付する
▶ 法務省のホームページもあわせてご確認ください。
▶ 法務省の資料PDFはこちら
以上、大まかな【相続土地国庫帰属制度】の概要をお届けしました。不要な土地を管理するには大きな負担がかかります。かといって引き渡し先を探し続けたとしても、大きな時間やコストがかかってきます。こういった面からも【相続土地国庫帰属制度】を利用することで、それらが軽減されるでしょう。
ただし制度を利用する場合でも、もちろん費用は必要です。そこで続く後編では、気になる「相続土地国庫帰属制度」の費用面について深掘りしてゆきます。どうぞお楽しみに!